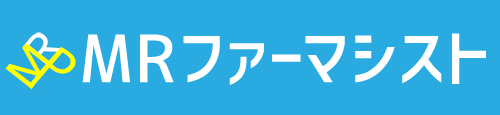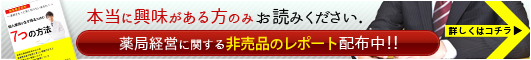MR・薬剤師限定
薬局経営のすべてが知れる無料メルマガ
ブラックボックス化された薬局経営の中身をすべて知りたくないですか?
500人以上へ10日間毎日配信。多くの方から届く感謝の声・・・
真実を書きすぎてブログでは公開できない内容をお届けしています。

「経済ゲーム」で読み解く行動経済学

ここで、ちょっとゲームをしましょう。
あなたは今大学生で、独り暮らしの大学友人から
引っ越しの手伝いを頼まれました。
この時、どの条件なら引き受けやすいですか?
①500円渡すから手伝ってくれない?
②引っ越しが終わったら、ワンコインランチ(500円)でもおごるよ。
手伝ってくれない?
③とにかく困ってるんだ。手を貸してくれないか?(何もお礼品はない)
結論的に言うと、一番お得なのは①でしょう。
現金でもらった方が、自分の好きなように使えるからです。
次に②で、報酬のない③は経済学的に不利な判断と言えます。
しかし、面白いことに、実験では、
③を選んだ人が最も多く、次に②、最後に①という順なのです。
(しかもこれ、世界共通の結果だそうです。)
でも、この結果、なんだか納得いくと思いませんか?
あなたの心の中のつぶやき・・・
「うーん。500円かあ。500円だと時給にしちゃあ、
ちょっと割に合わないよなア~・・・。それよか、友達とランチ一緒に行っておごってもらったほうが、
まだ気がラクだよね!そもそも、友達なんだからそんな水臭いことしねえで、
単に協力した方が、金銭がからまなくって、
こっちとしても気軽に手伝えるってもんだよな~」
こんな感じでしょうか。
このように、本来であれば①が最も合理的であるはずなのに、
経済的には不利な③をあえて選ぶ行為を考える学問を
「行動経済学」
といいます。
人間の考え方は完璧ではない「行動経済学」
この学問、2002年にノーベル経済学賞を受賞した
比較的新しい研究分野なのです。
(そして2017年にも行動経済学がノーベル賞を受賞しました!
詳しくは、コラム3回目より。)
それまで、経済学というのは、
「人間は、常に合理的に活動している」
という考えに基づいて研究されていました。
(伝統的経済学。ホモ・エコノミカス(経済人・エコン)は
利己的・合理的に自分の効果を最大化するという考え)
伝統的経済学というのは、人間の心理的な傾向を、
まるで高校物理の問題にあるように
「この時の速度を求めよ。ただし、空気抵抗は考慮しないものとする」
の空気抵抗のように無視していました。
それを覆したのが、経済学出身者でない
ダニエル・カーネマンと
エイモス・トヴェルスキー
でした。
(2017年ノーベル経済学賞受賞者の
リチャード・セイラー氏とは共同研究した
研究仲間です)
彼らは
「人々は経済学者が主張するほどには、
合理的に行動しないものだ」
と主張しました。
このエイモス・トヴェスルキーは残念ながら1996年に他界したため、
ノーベル賞を受賞したのはカーネマンだけでしたが、
(ノーベル賞は、受賞時存命の人間にしか賞をくれません)
彼はイスラエル出身のユダヤ人です。
 引用:Wikipedia
引用:Wikipedia
私は勝手に20世紀3大パラダイムシフト
(思想・発想の革命的変化)を
・ピカソの芸術
・アインシュタインの物理学
・カーネマンの行動経済学
の3人のユダヤ人がなしえたと考えています。
ユダヤ人のすごさを感じますね。
そして、21世紀に入ってからこの行動経済学を
投資など実際の経済活動に応用しようという研究
が急速に進んでいます。
このコラムでも、
5回シリーズである「投資と行動経済学」以降も
随時、行動経済学の考え方について
いろいろとご紹介していきたいと思います。
【市場規範】と【社会規範】を意識することはとても大切

さて、最後に話を最初のゲームに戻しましょう。
なぜ、人々は①より③がいいと思うのでしょう。
これは、人々が
【市場規範】(お金を支払ってのやり取り)
【社会規範】(ボランティアでのやりとり)
という2つの価値観を無意識のうちに同時に持っているからです。
ですから、「引っ越しのお手伝い」
という無償の行為(社会規範)から
500円と言われた瞬間に
頭の中が市場規範にバチッとスイッチが入り、
「それじゃあ割に合わねえ!」
と判断してしまったのです。
また、同じ500円でもモノ(現金)よりコト(友人との食事)
を重視するという人間の傾向も、研究によって明らかとなっています。
モノよりコトのほうが、満足度が高いのです。
(あ、ちなみに私も②を選びますかね~。
500円玉より友人とのワンコインランチの方がお得感あります♪)
お小遣い教育が、こどもに【社会規範】【市場規範】を植え付ける

この二つの概念を意識することは、
投資には直接結びつかないものの、実はとても大切なことです。
例えば、こどものお小遣いを
Ⓐお手伝いをしたらあげる報酬制
Ⓑお手伝いに関わらずあげる定額制
主に2つの考え方があり、各家庭でも実施していることでしょう。
これは、本当はこどもに
「お手伝いとは【市場規範】なのか【社会規範】なのか」
を教育しているとても大事なことなのです。
Ⓐの方針とは、
「お手伝い⇒労働である⇒【市場規範】と認識させる」
Ⓑの方針とは、
「お手伝い⇒家事・育児・介護などの無賃労働の一種である
⇒【社会規範】と認識させる」
というのを無意識に教育させているということなのです。
「えーー!?
そんなつもりはなかったのに…」
と思っているあなた。
今一度、自分はこどもにどちらの規範を認識させたいのか、
考えてみるきっかけになってくれたらと思います。
では、次回も行動経済学の経済ゲームをしながら、
その世界をご紹介しましょう。
管理人加納の独り言
『引っ越しゲーム』
とても面白い話でしたね?
あなたの答えはいかがでしたか??
私は
②番ですね。
EMIKOさんの答えに似ていますが
友達ということで
報酬よりも気持ちを重視します。
しかし人には
原理原則である
返報性の法則が働くのでGIVEされたら
返したくなるのが人間です。
友人関係の距離感を考えても
②番が一番しっくりきます。
まぁ人それぞれ性格がでそうですね笑